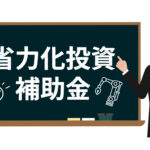労働基準法では、使用者に対して、労働時間を適正に把握・管理する責務を求めています。それにも関わらず、みなし労働時間制が認められているのはなぜでしょうか?
今回は、みなし労働時間制が認められている理由や背景について解説していきます。
みなし労働時間制とは?
労働時間の算定は、実際に労働した時間(実労働時間)によって行うのが原則です。この例外として、「実際に労働した時間にかかわらず、労働者が特定の時間を働いたものとみなす」ことが定められています。これを、みなし労働時間制といいます。
みなし労働時間制には、大きく「①事業場外労働に関するみなし労働時間制」と「②裁量労働制(専門業務型・企画業務型)」の2種類があり、労働基準法38条の2~4に規定されています。なお、「フレックスタイム制」は変形労働時間制の一種ですので、みなし労働時間制には含まれません。
みなし労働時間制が創設された背景
みなし労働時間制がどのような経緯で創設された制度なのか、簡単に説明します。
高度経済成長期を通じて、第三次産業の就業者数が伸び続けたこと。そして、技術革新の進展、経済のサービス化・情報化等に伴い、使用者の具体的な指揮監督が困難で、通常の方法による労働時間の算定が適切でない業務が増えたこと。こうした「時間では測ることができない新しい仕事」に従事する労働者が、労働時間の枠にとらわれず自主的・自律的に働けることを目指して1987(昭和62)年の労働基準法改正で創設されたのがみなし労働時間制です。
ちなみに、この年は、法定労働時間が週48時間から週40時間へ短縮されたり、フレックスタイム制が創設されるなど、現在の労働環境に近い改正が行われた年でもあります。
出張時の労働時間をどう考えるか
一般的に出張は、直行・直帰の場合には自宅を出発した時~自宅に帰着するまでが出張時間とされています。出張は、抽象的な使用者の支配下の業務遂行であるため、多くの会社で「事業場外労働のみなし労働時間制」として使用されており、「所定労働時間労働したものとみなす」ことが多いです。
「みなす」と「推定する」
労働関係の法律では、「みなす」と「推定する」という語が用いられます。両者は一見、同じ意味のように感じられるのですが、決まったことを覆せるか否かという点で明確な違いがあるため、条文上では使い分けがなされています。
「みなす」は、「本来は異なるものを、法律上は同じものとして取り扱う」という意味です。法的効果・権利義務を確定させるため、当事者がこれと違う事実を主張することはできません。例えば、労働基準法第38条の2では、下記のような規定がおかれています。
|
≪労働基準法第38条の2≫ |
ある労働者が労働時間を詳細に記録しており、後になって「実は、自分の時間外労働はこうだったんだ!」と申し出たとしても、反証は認められないため、所定労働時間が覆ることはありません。
労働基準法上では、「みなす」を用いている部分が全部で10か所あります。労使関係のトラブルが多いため、争いが生じた際でも、第三者(裁判所)の介入を待たずに、一刻も早く法的効果・権利義務を確定させられるように、という意図があります。
一方、「推定する」は、「反対の事実や証拠がない限り、ある事実について法令がとりあえずこのように取り扱う」という意味です。事実と異なる反証があれば、その推定の効果が覆される余地があります。例えば、労働者災害補償保険法第10条には、下記のような規定があります。
|
≪労働者災害補償保険法第10条≫ |
これは、船舶に乗っていた労働者が航行中に行方不明となって、その生死が3か月間分からない場合、その労働者は「とりあえず」行方不明になった日に死亡したものとして扱うというものです。ただし、後になってその労働者が生存していると事実確認ができた場合は、その事実に従うことになります。
みなし労働時間制は違法なのか?
労働基準法第32条では、「休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて、また、1日について8時間を超えて労働させてはならない。」と定めています。違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される規定があることからも、第32条が労働時間を算定する大原則であることが分かります。
また、労働基準法では、使用者に対して、労働者の労働時間を適正に把握・管理する責務を求めています。具体的に、第108条では使用者に賃金台帳を作成・保管する義務を課しています。この台帳には、労働日数や労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数などを記載しなければならないため、労働時間を把握・管理する必要があるということです。さらに、第24条では賃金全額払いの原則を保障しているため、やはり正確な労働時間を把握しなければなりません。
しかし、事業場外で業務に「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い場合」や、「裁量労働制において労働者を対象業務に就かせた場合」には、みなし労働時間制が認められます。なお、対象業務とは、業務遂行の手段および時間配分等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難・指示をしない業務のことをいいます。
以上の理由から、みなし労働時間制自体は、労働基準法に規定された制度であるため、違法ではありません。
しかし、ここで注意すべき点があります。
みなし労働時間制は、あくまで「労働時間の算定」に関して適用されるものなので、休憩・休日および深夜業の規定は排除されません。つまり、出張中であっても8時間を超えて労働させる場合には1時間の休憩を与えなければなりませんし、深夜時間(22時~翌日5時)に労働させる場合には深夜割増賃金の支払義務が生じます。また、1日8時間を超過するみなし労働時間を定める場合は、通常の労働時間制の場合と同様に「36協定の締結・届出」と「時間外割増賃金の支払い」が必要です。
このように、みなし労働時間制の運用については、法的に考慮することが多く、誤った運用を続けてしまうと違法とみなされ、労働基準監督署から指摘されるおそれがあります。そのような事態を防ぐため、専門家に意見を聞くことが大切です。弊法人では人事労務アドバイザリー業務をおこなっております。判断に迷った時はぜひ弊法人にご相談ください。
人事労務アドバイザリー - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所
また、「顧問契約というほどではないが専門家に相談したい」といった、スポット的なアドバイザリーも弊法人ではお受けしております。企業様のご相談のほか、個人の方からのご相談についても、元労働基準監督官である弊法人の代表がご相談内容を伺い、ご状況を踏まえつつ個別のアドバイスをさせていただきます。