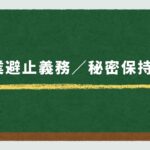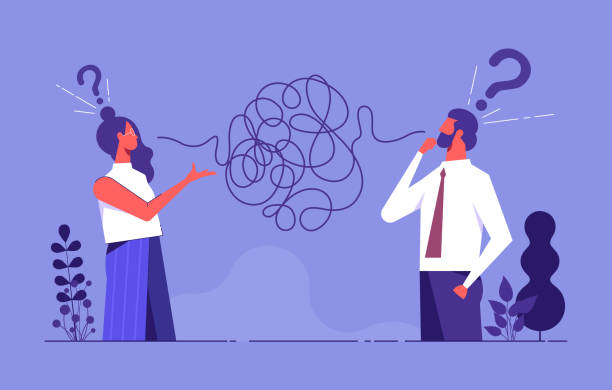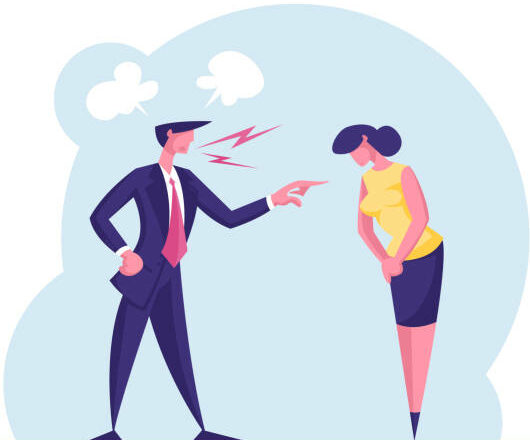セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなど多種多様なハラスメントについて問題視され、企業は対策をとっていくことが急務となっています。ハラスメントにつながる認知の偏りとして「アンコンシャス・バイアス」が挙げられます。Googleなどアメリカの大手企業が「アンコンシャス・バイアス」対策を取り入れるなど、海外はじめ、日本でも注目されている概念です。では、「アンコンシャス・バイアス」とは具体的にどのようなものなのか、また実際に企業で起こりうる事例とその対策について学んでいきましょう。
アンコンシャス・バイアスとは、心理学の概念である「認知バイアス」の一つで、無意識の偏見や思い込みから偏ったものの見方をしてしまうことです。「男性は仕事第一でいるべきだ」「女性は仕事をやめて家庭に入るべきだ」などといった考え方がアンコンシャス・バイアスの一例です。多くの人はその考えをアンコンシャス・バイアスとは認識せず、無意識のうちに他人を傷つけたり間違った判断をしていたりする可能性があります。人間の脳には素早く効率的に情報を処理しようとする脳の性質があり、日常生活の膨大な量の情報を処理するために、過去の経験や環境に基づいて情報のカテゴリー化や一般化を行うため、このような無意識の偏見は日常にあふれています。
アンコンシャス・バイアスの種類
アンコンシャス・バイアスにはいくつか種類がありますが、そのうちの代表例である以下6種類を紹介します。
①ステレオタイプバイアス
性別や国籍などの属性に対する先入観や固定観念に縛られてゆがめられた判断や行動をすることです。男だから、女だからというジェンダー、皮膚の色や職業、年齢などによる個人の偏見でもって人と接し判断してしまう危険性があります。
| 例)女性は家庭を守るべきなので、子どもが生まれたら仕事をやめるべきだ |
②正常性バイアス
予期しない出来事が起こった時、無意識のうちに正常の範囲内であるととらえることで、心を平静に保とうとすることです。ストレスを回避するために働く人間の防御反応の一種ですが、このバイアスが働きすぎると、深刻な事態であるのに認知できずに被害が拡大してしまうおそれがあります。ハラスメントの被害者に多い心理傾向といわれており、このバイアスにより、我慢を重ね精神的障害を抱えてしまうことがあります。また、災害時に逃げ遅れるのは正常性バイアスによるものといわれています。
| 例)業績が落ちているが「なんとかなるだろう」と何も対策をとらない |
③集団同調性バイアス
集団内にいると他者と同調して同じ意見や行動をとりやすい心の働きです。日本人はこの働きが特に強いといわれており、企業内の意思決定において、グループの意見に同調することが多く、新しいアイディアや異なる視点を取り入れにくくなる危険性があります。また、ハラスメントのある組織の場合、ターゲットである一人がハラスメントを受けている場合に、周囲もそのハラスメントが起きている組織の体質に同調してしまうケースが考えられます。
| 例)上司から部下へのパワーハラスメントが常態化しているが、誰も意見できない |
④確証バイアス
自分が正しいと思う先入観や意見を肯定する情報ばかり集めて、否定的な情報を排除してしまうことです。ビジネスの場面に限らず、SNSや医療、政治など日常生活のあらゆる場面で起こりうるバイアスです。
| 例)自分の意見に従う部下を優秀だと決めつけて評価する |
⑤現状維持バイアス
知らないことや経験したことのないことを受け入れず、現状維持を好む心理的傾向です。変化をすることに恐れをいだき、重要な決断であるほど現状維持を好むといわれています。特に利益より損失を回避することに優先して行動している人間の性質が影響を与えています。
| 例)社内で反対の声があり、新しい商品やサービスの導入になかなか踏み出せない |
⑥権威バイアス
社長や管理職など、組織において権威の高い人の意見を優先し正しいと思い込むことを指します。対して一般社員など権威の低い人の意見は有益であっても無視されてしまいます。このようなバイアスがある組織では、従業員は自ら考える力を失うため、成長機会がなくモチベーションも下がるので、企業全体の成長が拒まれてしまいます。
| 例)社長の意見は常に正しいはずだから、従うべきだ |
以上のことから、「多くの人にとって当たり前」とされている個人の「アンコンシャス・バイアス」が「社会・組織にとって当たり前」と認識されることで、他者に対して「○○すべきだ」「〇〇であるはずだ」と判断し相手を傷つける言動をしてしまう可能性があります。それにより、相手を傷つける意図がなかったとしてもハラスメント行為につながる可能性があります。
職場で多いアンコンシャス・バイアスの例
職場で起きるアンコンシャス・バイアスは、業務中の他に、人事評価や採用活動、人材育成など、あらゆるシーンで起きます。以下が職場で生じがちなアンコンシャス・バイアスの一例です。
|
・女性は仕事より家庭を優先するものだ ・出世を望む男性は仕事を優先するはずだ ・短時間社員は仕事より家庭が大切だと思う ・育児や介護は男性より女性が向いている ・受付やお茶出しを男性が行うのはおかしい ・最近の若者は根性が足りないと思う ・シニア世代はパソコンが苦手だ ・良いアイディアを思いついたが、皆が指示しているアイディアに賛同する ・業務中にミスを見つけたが、誰も指摘しないので放置する |
アンコンシャス・バイアスがビジネスに与える影響
アンコンシャス・バイアスは組織の風土形成に悪影響なだけでなく、ビジネスの機会損失や、ハラスメントが発生した場合の企業イメージの低下など、対内部だけでなく対外部においても問題を引き起こしてしまうおそれがあります。
①ビジネスの機会損失
偏見に基づいた判断により、新しいイノベーションの機会や優秀な人材の採用を見逃す可能性があります。また、特定のターゲット層に対して偏見がある場合、その層のニーズを見誤ってしまい、適切な商品・サービスの価値提供ができなくなるおそれがあります。
②コミュニケーションの抑制
出身地や性別、年齢などへの無意識の偏見が言動にあると、排除されたと感じる人がいる場合、良好なコミュニケーションをとるのが難しくなります。また、そういった個人のアンコンシャス・バイアスが組織の共通認識・習慣となり社内風土として定着してしまうと、社内の雰囲気が悪くなる、パフォーマンスが低下するなど起こるリスクが生じてしまいます。
③ハラスメントの増加
従業員にアンコンシャス・バイアスへの認識がないままにコミュニケーションをとることで、セクハラ、パワハラなどのハラスメントの原因となることがあります。
また、そういった無意識の偏見に対して従業員が同調することで、社内風土の悪化につながり、ハラスメントの増加を引き起こしてしまいます。
ハラスメントを防ぐために~アンコンシャス・バイアスの活用~
では、アンコンシャス・バイアスに対して、企業内ではどのように向き合っていくとよいでしょうか。上記に挙げた通り、アンコンシャス・バイアスは無意識的な思い込みであり、完全になくすことはできませんが、従業員一人ひとりがアンコンシャス・バイアスの存在を認識し、行動を変え、組織として仕組みを変えていけるように、対策をたてていくとよいでしょう。
具体的には以下の対策が挙げられます。
1)アンコンシャス・バイアスの理解促進
まずは従業員一人ひとりが「アンコンシャス・バイアス」を認識することが重要です。研修やワークショップを行い、自分自身のバイアスを知る機会をもつ、ハラスメントの事例を通してどう感じたか、ディスカッションを行うとよいでしょう。
2)職場内コミュニケーションの工夫をする
職場内の何気ない会話の中で無意識の偏見がハラスメントにつながることがあるため、意識的なコミュニケーションの工夫が重要です。例としては以下のような対応が挙げられます。
・無意識に差別的発言となるものを避け、事実に基づいた伝え方をする
「女性の割に…」「男性だから…」「若いから…」などのバイアスに基づく発言を避け、「○○の経験が豊富だから…」など客観的な事実に基づいて発言するようにする。
・多様な視点を尊重し、チーム内の多様性を高める
会議の発言などでいつも意見を言う人ではなく「発言意見の少ない人」にも意見を求め、特定の人の発言力が高くなったりとバイアスが影響しないよう、多様性の尊重される組織をつくる。
・「共感」を意識した関わりを心掛ける
「もし自分が相手の立場だったらどう思うか」を基準にし、受け取る相手視点での発言を心掛ける。
3)アンコンシャス・バイアスを意識した取り組みを行う
また、個人だけでなく組織としてバイアスを減らす仕組みづくりをしていくことでハラスメントの起こりにくい環境を作ることができます。具体的には以下のような対策をしていくのが効果的です。
・職場環境の見直し
「男性だから・女性だから○○」「上司だから、部下だから○○」といった固定観念による役割分担をなくす、結婚、育児や介護などのライフイベントを公平に扱う制度を整える。
・採用、人事評価、昇進プロセスの基準の明確化や透明な評価制度の整備
個人のバイアスが評価に影響しないように評価基準を明確化・客観化する。複数人が評価する体制を導入するなど、評価方法を個人のバイアスによってゆがめられないようにする。
・ハラスメント発生時の対応フローの明確化
社内外に相談窓口を設置し、ハラスメントが起きた際も従業員が抱え込まずに相談しやすい仕組みを作る。
これまでに「アンコンシャス・バイアス」の起きる仕組みや具体例、そこから起こりうるリスクとその対策について解説してきました。しかし、「アンコンシャス・バイアス」は誰もが日常的にもっており、「無意識」に行われているためすべてのバイアスをなくすことは難しいでしょう。また、「アンコンシャス・バイアス」に基づいた言動をする当事者が、常に相手に対して悪意をもっているわけではないでしょう。「アンコンシャス・バイアス」を過剰に意識するあまり、組織内でのコミュニケーションがとれなくなることも問題です。
まずは「アンコンシャス・バイアス」の存在を知り、自分にどんな傾向があるかを知ること、また、組織内外で他者と関わるときに相手視点を忘れずに発言することが大切です。そうすることで、普段から良好な関係を築くことができるため、万が一バイアスに基づいた発言があったとしても、互いにコミュニケーションを円滑にとることができ、未然にハラスメントを防ぐことができます。
上記に挙げたようにアンコンシャス・バイアスを意識した職場環境の整備や、人事評価制度の構築はハラスメント対策として効果的です。こういった働きやすい環境の整備にあたっては、事業の実態を踏まえてアドバイスができる、経験豊富な専門家に相談しながら進めていくことが重要です。
弊法人では、事業主の事業特性や組織風土に合った運用しやすい制度構築の支援を行っております。ぜひご活用ください。
制度構築 - プラットワークス|社会保険労務士法人プラットワークス|東京都 千代田区 大阪市|社労士法人 社労士事務所
また、弊法人では、「社会保険労務士」と「臨床心理士(公認心理師)」の協同で支援を行う、日本唯一の企業向けオンラインカウンセリングサービスPlattalksを運営しております。従業員にとって、相談することで心の負担を軽くする外部の相談窓口として活用いただくことができます。
Plattalksではカウンセラーによる従業員のメンタルヘルスケアを行うだけでなく、相談者の希望に応じて社会保険労務士との連携、相談対応も行っており、働きやすい体制構築に活用することができます。
Plattalks - 社会保険労務士法人 プラットワークス - 東京都千代田区・大阪市北区の社労士法人 (platworks.jp)