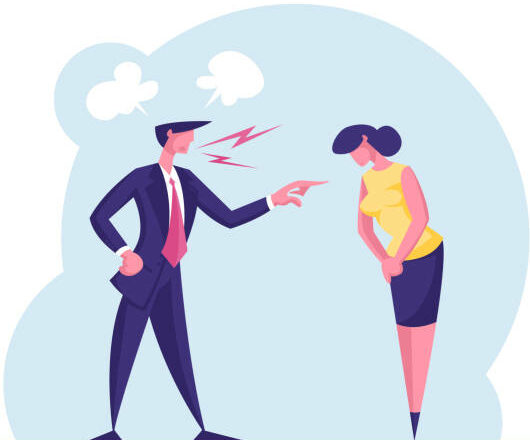もくじ
「最近、部下の表情が沈んでいる気がする。」
「急に遅刻や欠勤が増えた。」
「ミスが増え、報連相も減っている。」
管理職の皆さん、部下にこのような違和感を感じたことはないでしょうか?
これは、単なる”やる気の低下”ではなく、適応障害の初期サインかもしれません。
適応障害は、明確なストレス要因に対し、心や身体が適応しきれず、不安・抑うつ・回避などの症状が現れる状態です。
放置するとうつ病や不安障害といったより深刻な疾患に進行することもあり、早期対応が極めて重要です。
本コラムでは、心理学の観点から、
・「なんとなくおかしい」と感じた時の初期対応
・診断が必要か迷った時の見立てと判断
・職場でできる環境調整や関係性の支援
・管理職自身の心のケア
まで、実践的に解説します。
1 適応障害とは?ーうつ病との違いー
適応障害とは?
適応障害とは、ある明確なストレス要因(人事異動・職場内の人間関係の変化・家庭問題など)に反応して、情緒的または行動的な症状が出現し、生活や仕事に支障をきたすストレス関連障害です。
心理的な耐性を超えた出来事に対して一時的に心身が適応できず、本人の「いつもの調子」が崩れる状態とも言えます。
DSM-5における診断基準
米国精神医学会の診断基準(DSM-5)では、以下の条件を満たすと、「適応障害」と診断されます。
1.明確なストレス因にさらされた3ヶ月以内に症状が出現
2.その反応が以下のいずれかを伴う
ー社会的・職業的な機能の著しい障害
ーストレス因の影響としては過度な苦痛がある
3.他の精神疾患(例:うつ病、PTSD)では説明できない
4.症状はストレス因が取り除かれてから6ヶ月を超えて持続しない
うつ病との違い
適応障害はうつ病とよく似た症状が現れることがあります。
しかし、適応障害はストレス因である環境や人間関係から離れることで症状が現れない一方、うつ病は常に症状が持続するという点で大きく異なります。通常、適応障害は6ヶ月以内で症状が改善することが多いのですが、適応障害が長期間続いたり、ストレス要因が解消されないままだったりする場合、うつ病に移行することもあります。そのため、うつ病の手前の段階とも言われ、症状が軽くても気は抜けません。”今、気づいて支援すること”が重症化の予防につながります。
| 比較項目 | 適応障害 | うつ病 |
| 原因 | 明確なストレス因がある | ストレス因が不明瞭なことも多い |
| 発症時期 | ストレス発生から3ヶ月以内 | 時期や誘因が曖昧なことも多い |
| 症状の強度 | 中等度で波がある | 重度かつ持続的(希死念慮など) |
| 典型症状 | 不安、落ち込み、回復、無気力など | 抑うつ気分、興味喪失、自責感、睡眠・食欲の変化など |
| 持続期間 | ストレス因が除去されれば比較的早く改善 | 数ヶ月以上続くことが多い |
| 治療方針 | 環境調整と心理的支援が中心 | 医療的介入(薬物治療含む)が基本 |
2 初期対応ー「責めずに気づく」がスタートライン
部下の変化にいち早く気づくことは、管理職の大きな役割です。ただし、「元気がない」「業務パフォーマンスが下がった」からと言って、すぐに問い詰めるのは逆効果です。
観察すべき初期サイン
・表情が乏しく、会話が減る
・遅刻・早退・欠勤が増える
・ケアレスミスが増加し、報連相が減る
・否定的・悲観的な発言が増える
・「疲れた」「頑張れない」といった言葉が目立つ
声かけのポイント
・「最近、ちょっと心配で声をかけたんだけど…」という関心ベースの言い方
・「何があったの?」よりも「何かしんどいことある?」という共感的な接近
・指導・評価を切り離した安心できる場の提供
声かけは、臨床心理学における「カウンセリングの3つの基本的態度」を基に行います。これは心理学の巨匠と呼ばれるカール・ロジャースが提唱した「受容・共感・自己一致」の3つの態度を指します。
「受容」とは、相手に批判や否定的な目を向けず、ひとりの人間として大切に思いやって話を聞こうとする態度です。
また「共感」とは、相手のものの見方や考え方に沿って相手を理解し、それを示すことを指します。
そして「自己一致」とは、聴き手自身が心理的に安定していて、言動を一致させて関わることです。
この3つの態度は、カウンセリングの場面だけではなく、管理職と部下の関わりにおいても、信頼関係を構築し、部下に理解と安心感を提供することに役立ちます。
3 判断と連携ー「診断しない、でも放置しない」
部下が抱えているストレスや不満が明らかになった時、診断を下すのは医師の役割です。
管理職は、”支援へつなぐ橋渡し”という立場でいることが求められます。
❌やってはいけない対応
・「それくらいみんなあるよ」と一般化
・「休みたいの?」と探るような口調
・「気持ちの問題でしょ」と切り捨てる
⭕️適切なアプローチ
・産業医・社内カウンセラー・心理職との面談を提案
・「診断が出る=休職」と決めつけない安心感の提供
・本人のペースを尊重しつつ、支援の選択肢を複数提示
不調を「本人の弱さ」ではなく「人と環境の相互作用の結果」と捉える”エコロジカルシステム理論”の視点が重要です。
これは、アメリカの発達心理学者である、ユーリ・ブロンフェンブレンナーが提唱した理論で、個人を環境から切り離して捉えるのではなく、個人と周囲の環境との相互作用という視点で包括的に捉える考え方です。適応障害においては、その症状のみを一面的に見るのではなく、本人が置かれてる環境(職場、家庭など)の構造や人間関係、社会的な支援の有無など、多面的な環境要因にも目を向けることで、症状の先にある本人の全体像が見えてきます。
管理職がこのような視点を持つことで、部下へのより深い理解と包括的サポートが可能になります。
4 職場でできる対応ー無理をさせない。でも孤立させない
実際に適応障害と診断された部下に対して、管理職は具体的にどのような対応をすれば良いでしょうか?ポイントは「無理をさせない」「孤立させない」の2点です。
心理学的に効果的な対応策
| 対応 | 内容 |
| 環境調整 | 業務量の軽減、期日緩和、業務内容の一時変更 |
| 安心感の提供 | 定期的な1on1でのチェックイン、感情のモニタリング |
| 所属感の保持 | 「また戻ってきていい」空気づくりと、自然な声かけ |
| 周囲の配慮 | 過度な詮索や「特別扱い」の防止(本人の同意を得た上で共有) |
職場における「心理的安全性」が、不調からの回復に大きく寄与します。
心理的安全性とは、組織行動学者のエイミー・C・エドモンドソンが提唱した、メンバーが対人関係のリスクを恐れず、安心して発言・行動できる状態のことです。心理的安全性が高い職場では、「休むことは迷惑ではない」という認識が共有されており、本人が過度な罪悪感や焦りを感じることなく、回復に専念できます。
また、相談しやすいオープンな文化が醸成されているため、率直な感情の共有と孤立の防止につながります。そして職場復帰後も、本人が再発への恐れを克服し、再び活躍するための土台となります。
このような職場文化の醸成には、日々の継続した取り組みが必要です。
管理職のみならず組織の一人ひとりが「他者の意見を受け入れる姿勢」「失敗を責めない」「感謝を伝える」などの意識を持つことで、心理的安全性が組織文化として根付きやすくなります。
心理的安全性についてもっと知りたい👉心理的安全性を高めるために〜みんなが活躍できる職場づくり〜
5 支援側のケアもー管理職こそひとりで抱え込まないで
部下のメンタル不調に向き合う中で、支援する側のストレスも見逃せません。
・「自分のせいかもしれない」という自責感
・感情に巻き込まれることによる疲労
・周囲に相談できず孤立する感覚
これらは「共感疲労」と呼ばれる状態につながる可能性があります。
共感疲労は、ベトナム戦争帰還兵のPTSD(心的外傷後ストレス障害)などを研究している、アメリカの心理学者学者チャールズ・フィグレーが定義した考え方です。
他者の苦痛に深く共感しすぎた結果、自分の心身が消耗してしまう状態のことをいいます。
具体的な症状としては、無気力になる、気分が沈みがちになる、イライラしがちになるなどが挙げられます。
この状態は、部下のつらい話を聞く機会が多い上司が陥りやすい傾向があります。部下との円滑なコミュニケーションにあたって「共感」は重要な能力です。しかし、共感も過度に働くことで、逆に支援機能の低下を招いてしまうため、注意が必要です。
できるセルフケアと外部支援
・管理職間での事例共有やピアサポート体制の構築
・外部の心理職やカウンセラーへのコンサルテーション
・「相談していい立場」としての自己認識を持つこと
支援の質を高めるには、「支援側の安心」が不可欠です。
管理職自身のメンタルヘルスも守られるべき大切な資源です。「支援側として不安を抱えることは未熟ではない」という認識を持ち、自分の感情を自覚し、吟味することで、感情に振り回されずに支援を続けることができます。
心身の疲れに気づいたら、無理をせず休息を取得するようにします。また、問題は 一人で抱え込まず、必要に応じて会社の相談窓口や産業医など、専門家に相談することをためらわないようにします。
そして重要なのが、 支援対象者への過剰な介入を避け、適切な距離感を保つことです。責任の境界を意識することで、過度な負担から自己を守ることにつながります。
6 まとめー”対話”から始まる予防と再生
適応障害は「甘え」でも「心の弱さ」でもありません。誰にでも起こりうる心の反応であり、早期に気づき、声をかけることが、回復と信頼の第一歩になります。
「話を聞く」「無理をさせない」「孤立させない」その基本姿勢が、職場の心理的安全性とエンゲージメントを高め、結果として離職防止・生産性向上にもつながっていくのです。
7 終わりに
メンタル不調は、特別な誰かにだけ起こることではありません。
日々の小さな負担やプレッシャー、職場での人間関係や役割の重さ…それらは、部下にも、それを支える管理職にも、静かに積み重なっていきます。
「職場の中で話せないことを第三者に安心して打ち明けられる場所がある」。
それは、不調の予防や早期対応、そして次の一歩を踏み出す力になります。
「プラットトークス」は、そんな”話せる場所”を職場の外に用意するサービスです。
臨床心理士・公認心理師などの専門家が、オンライン・匿名でいつでも相談に応じます。
企業の福利厚生として導入いただくことで、それぞれの立場に応じた心理支援や、適応障害の予防・早期対応、さらには”予備軍”への継続的ケアまで可能になります。
管理職も部下も、ひとりで抱え込まずに済む組織づくりのために。どうぞご活用ください。